えこりん、ザッキーが最も愛する作家・宮本輝さん。
その作品の数々をご紹介してゆきます。
まずは最新刊から、そして遡っていきます。
1947(昭和22)年、兵庫県神戸市生れ。追手門学院大学文学部卒業。広告代理店勤務等を経て、1977年「泥の河」で太宰治賞を、翌年「螢川」で芥川賞を受賞。その後、結核のため2年ほどの療養生活を送るが、回復後、旺盛な執筆活動をすすめる。『道頓堀川』『錦繍』『青が散る』『流転の海』『優駿』(吉川英治文学賞)『約束の冬』『にぎやかな天地』『骸骨ビルの庭』等著書多数。ーーAmazonより
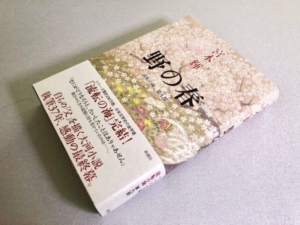
野の春
10/31に発売された宮本輝著『野の春』を読了しました。
宮本輝自身の父をモデルにした自伝的大河小説流転の海 第9部 野の春です。長い長い年月をかけて、ついに完結! いや〜、本当に長かった。
と思ったら、なんと37年も経っていた!
一つのテーマで書き続けるのは、作者はもちろん大変だったでしょうが、待ち続けた読者もアッパレです(私を含む)。
小説というと、最近はライトノベルとか、軽めのミステリーとかが主流で(ミステリーは私も好きですが)、こういう純文学は今や希少かもしれないですね。
主人公の松坂熊吾が五十歳にして授かった一人息子の伸仁は大学生になり、二十歳の誕生日を迎えます。
「この子が二十歳になるまでは絶対に死なん」という熊吾の誓いは成就したのですが、、、。
事業を興しては失い、興しては失い、常に人を助けながら、裕福な暮らしから貧乏な底辺の生活に落ち、また立ち上がる。
そんな熊吾と妻、房江の波乱万丈の人生の中で、生きる意味とは何か、宿命とは何かを考えさせられます。
「お天道様ばっかり追いかけるなよ」とか、「なにがどうなろうと、たいしたことはありゃあせん」といった、熊吾の言葉も心に残ります。
慈雨の音
作家・宮本輝のライフワーク『流転の海』の第六部『流転の海 第6部 慈雨の音』が、ようやく刊行された。第一部が1984年に刊行されてから27年。
前作の第五部『流転の海 第5部 花の回廊』からも3年。まだ完結は遠そうで、こうなると作者と読者の根比べのようでもある。「自分が生きているうちに完結して欲しい」という長年の愛読者の声も…。
時は昭和34年。終戦から14年がたち、日本がめざましい復興をとげていた頃だ。皇太子御成婚や日米安保、東京オリンピックのニュースに日本中が湧いていた。
松坂家でも、御成婚パレードを見るために、テレビを購入した。
冷蔵庫や洗濯機も普及し始め、ようやく戦後の混乱期が終わって、高度成長期が始まろうという頃だ。『週刊少年マガジン』、『週刊少年サンデー』もこの年に創刊されている。
松坂熊吾の駐車場経営は軌道に乗り、新事業に手を広げていく。妻の房江も、生活に喜びを見いだしてゆく。
中学生になった一人息子の伸仁は思春期を迎え、親に反発したりもする反面、子犬や鳩を飼う心のゆとりも見える。
一方、「地上の楽園」と喧伝された北朝鮮へ帰還する人々との、つらい別れもあった。何人かの登場人物の中には亡くなる人も。
今回、非常に重要な場所として山陰本線に架かった余部鉄橋が登場する。この橋の上から自分の遺灰を撒いてほしいという浦辺ヨネの遺言を果たそうとする松坂一家だ
が、下は千尋の谷で、普段剛胆な熊吾も怖じ気づくほど。そこで、伸仁はもう一つの別れも経験した。
相変わらず、熊吾の人生哲学がしみ出すかのような言葉の数々も必読。しかし、妻の房江は、熊吾とは違う人生観に悩んだりもしている。
まだ生々しく残る戦争の記憶と、確実に復興へ向かう時代の大きなうねりの中で、成長してゆく伸仁と、伸仁に限りない愛情を降り注ぐ熊吾。
「父と子」を描く作者の自伝的物語は、これからも続く。
三千枚の金貨(上・下)
そんな謎に満ちた言葉を残して去った見知らぬ入院患者。同じ病院に入院していた斉木は、訳がわからないままに、その言葉を暗記していた。
それから五年、思い出しもしなかった男のことが、なぜか長い旅の途中で蘇った。
あの言葉は本当だったのではないかと思い始めた斉木は、マミヤ三銃士と呼ばれる親友、川岸と宇津木、バーMUROYのママ、沙都とともに、金貨の行方を追う。
沙都は、斉木が謎の男に出会った病院で、当時看護師をしていた。沙都は何かを知っているかもしれない…。
男は誰なのか。約一億円もの価値がある金貨を、なぜ桜の木の下に埋めたのか。なぜ、その話を縁もゆかりもない斉木にしたのか。
謎は深まるばかりだが、物語は単なる宝探しではなくなっていく。
斉木が旅したタクラマカン砂漠。そこで生きていた人々。消えた大河。西域北道のゴビ灘に消えていった少年。カラコルム山系の中のフンザの星空。そして星を見ながら感じた「慈愛」という言葉でしか表現でき得ないもの。
施しが「慈愛」なのではなく、命を生み出し続け、それを養い活かしている何かが慈愛だと斉木は気付くのだ。
謎の男の人生を追ううちに、次第に浮き彫りにされる「生きること」の意味。
三千枚の金貨が呼び寄せた、少しの非日常が、平凡な日常までも、くっきりとしたものに変えて行く。酒やゴルフの蘊蓄も楽しい。
斉木の旅の記憶と重なって、宝探しは思わぬ方向へと進んでいく。
過去に生きた人たち。今生きている人たち。生きているというすごさ。
特にすごく大きな事件は起こらないけれど、いつもの宮本文学のように、淡々と面白い。
花の回廊 流転の海 第5部
宮本輝のライフワーク、流転の海 第5部 花の回廊 (新潮文庫)。着手から25年を経て、主人公の松坂熊吾は還暦を過ぎ、熊吾が50歳で授かった息子の松坂伸仁はようやく11歳になった。
35歳で『流転の海』を書き始めた著者も還暦を過ぎ、やっと熊吾の年齢に追いついた、と後書きにある。 著者自身の自伝的小説。
昭和32年、財産を失って無一文になった熊吾は、電気も水道も止められた大阪・船津橋のビルで暮らしながら、来る自動車社会を見据えて、巨大モータープールの設立に奔走していた。
妻、房江は辛い思いをしながらも小料理屋で下働きをして家計を支えている。
だが、小学生の伸仁とそのビルで暮らすことは難しく、伸仁は熊吾の妹、タネに預けられる。
タネは、尼崎の貧しい人たちが住む、迷路のような構造の奇妙なアパートに暮らしていた。
そこには虐げられた朝鮮人やヤクザや売春婦、自殺を図る男など、貧しすぎる人たちの壮絶な人生があった…。
第1部発行時には、全5部で完結のはずだったと思うのだが、当初の予定をはるかに越えて、より壮大な物語になっている。
今後は伸仁が中学生、高校生、大学生となってそれぞれ1部ずつで、熊吾が70歳で亡くなって完結予定だとか。第六部は現在熟成中とのこと。
早く熟成して欲しいものだが…。
にぎやかな天地
「日本の発酵食品を後世に残すための本を作って欲しい」。
豪華限定本編集者、船木聖司は、謎めいた老人、松葉伊志郎からそんな依頼を受けた。
すでに一般の家庭ではなじみが薄くなっている糠漬、鰹節をはじめ、醤油、味噌、酢、熟鮓など…。
日本中を取材して回るうちに、聖司は目に見えない微生物の、思いもよらぬ偉大な営みに気づいていく。
聖司は発酵食品の取材をしながら、自らも乳児のころ、母の乳が足りずに、発酵食品であるチーズで育ったことを思い出す。
それを与えてくれた亡き祖母と、祖母が最後に残した「ヒコイチ」という謎の言葉。 三十二年前に亡くなった、聖司の父親とその死に関わった男性の謎。
それらが絡み合って、聖司は、愛してはならない二人の女性と出会う。
微生物が長い時を経て、何かをもっと豊穣な別の物質へと生まれ変わらせるように、人生も変化し、憎しみや哀しみさえも、別の何か豊かなものへと変わっていく。
すべては熟成する。きっとそういうことなのだ。
人生も、哀しみも。毎日糠床をかき混ぜるように、自分の人生も日々、心を込めて生きていれば、いつかその実りを受けられるのかもしれない。
生きていれば、当然つらいことも苦しいこともあるけれど、それらもうまく熟成させることが出来れば、幸福に変わる。
今、大きな苦しみに遭遇している人も、死にたいほど悩んでいる人も、十年後、二十年後、豊かな実りを得られるかもしれない。













